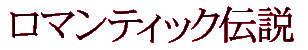
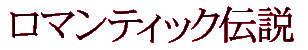
7
数日後。
約束の時間の10分前に神波が冨永商店の前へ行くと、もう既にみきが待っていた。神波の姿を認めてぺこりとお辞儀する。
「こんにちは、早いですね」
「君こそ」
そう言って笑って、神波は彼女の持っている袋に目を止めた。
「どしたの、それ」
「あ、これですか?」
みきは笑って袋を持ち上げてみせる。
「聡子さんに話したらお店のものいろいろくれて。ちょうどお昼時だしって。ほんとは私がお弁当でも作ればよかったんですけど」
「そんな気使わなくてもいいよ。悪いなあ、いつももらっちゃって」
「ほんと、いつも私もお世話になってるんですよ」
ふと会話が途切れて神波は頭を掻いた。
「........どう、しましょうか」
「そうだね」
「お弁当出来るとこがいいですね。お弁当って程じゃないですけど」
「じゃあ、神社の境内んとこ行こっか。昼間なら明るいよね」
「はい」
二人は境内の階段に並んで腰を下ろした。パックのジュースやパンを一緒に食べる。
「外で食べると気持ちいいねー」
「そうですね、天気もいいし」
「ねえ」
「はい?」
神波は少し言い淀んでから切り出した。
「聞いてもいいかな、なんでみきちゃんってあんなとこで働いてんの?」
「意外ですか?」
「あ、いや、ごめんね、別に店がどうってんじゃないんだよ。たださ、あの.....」
「いいですよ」
みきが笑う。
「.......実は、こないだみたいなことって、あれが初めてじゃないんですよね。今までにも何度かあったんですよ」
「.......うん」
「うちって女系家族だし、女子高だったりしたからあまり男の人って縁なくて。でここに来てあんなことがあったりしたから余計男の人怖かったりして。田舎ではあんなことなかったし」
「田舎って、どこなの?」
「岡山です。知ってます?ちょっとマイナーなんですけど。桃太郎伝説のとこですよ」
「ああ、えっと........水島工業地帯」
神波の言葉にみきは思わず吹き出した。
「俺なんか面白いこと言った?」
「だって、そんな風に言われたの初めてで」
「そんな涙流してまで笑うなよー」
「ごめんなさい、だっておかしくて」
「ちぇ」
神波がむくれてみせると、みきは少しの間笑い続けて涙をふいた。ジュースをひとくち飲んでから神波に向き直る。
「........怒っちゃいました?」
「冗談だよ、ふざけただけだってば」
「よかった」
「学生だって言ってたよね、上京して何勉強してるの?」
「絵です」
「絵かー、凄いなー」
「黒井健ていう画家がずっと大好きで。知ってます?」
神波は申し訳なさそうに笑った。
「ごめん、知らないや」
「いいえ、そんなにメジャーな人じゃないですから。こういう絵描く人なんです」
みきはそう言うと鞄の中から一冊の絵本を取り出して神波に見せる。新見南吉の『ごんぎつね』。
「小学校とかで習ったと思うんですけど」
「うん、これ絵見たことあるよ。話も知ってる。すんごい寂しい話なんだよね」
「そうですね、なんか、私の中でバイブルなんですよ。この人の絵、凄く懐かしくて暖かい感じがして、こんな風に描けたらなあって」
神波は本をぱらぱらとめくった。
「そうだね......なんか、望郷の念が蘇る感じする」
「ええ。でね、学校はここから少し離れたとこなんですけど、学校とは別にひとり絵を教えていただいてる人がいるんです。その人がここの近くに住んでて」
「うん」
「その人が今住んでるアパートもバイト先もその人が紹介してくれたんですよ。仕送り少ないですから、出来るだけお金浮かせたくて」
「........凄いね」
「バイト代は全部絵関連で消えちゃいますからなるべく安いとこって。時々怖いですけど」
「そりゃあ、そうだろうね........」
黙り込んだ神波をみきが覗き込む。
「どうしたんですか?」
「いや.......偉いなあって思って。俺なんかとは大違いだよ」
「そんな、偉くなんかないですよ」
「.........俺の話も、聞いてくれる?君程凄くもないし、ちょっと怖い話とかしちゃうかもしれないけど」
みきは膝を抱え直して笑った。
「聞かせて下さい。気に障ったらすみませんけど私も実は思ってたんです、なんか、神波さんてこの街にはあまりそぐわないなあって」
「.......こんなこと組の人以外で自分から話すなんて、みきちゃんが初めてだよ」
食べかけのパンを一気に押し込むと、神波は話しはじめた。
「...............」
話を一通り聞き終えたみきは、暫く考え込んだ。
「俺って、そんな奴だったんだよ。みきちゃんとは大違い」
「.........大変、だったんですね.......」
「族なんかで無駄に時間使っちゃって自分が恥ずかしいよ、みきちゃんの話聞いたら。それに俺一応前科ありの人間だからさ。もうまっとうになんか生きれないよ」
「そんなこと、ないです」
自嘲気味に呟く神波にみきは強い口調で言う。
「誰だって間違いはあるじゃないですか。それに過去はもう変えられないんですから、これからの時間を大事にすればいいんですよ。星野さんだって、神波さんのそういうとこを見込んで下さったんじゃないんですか?」
「うん.....そうだといいけど」
「私は神波さん達の世界よく知らないですから、偉そうなこと言えないですけど」
「偉そうでもなんでもないよ、ありがとう」
「それに.......」
俯いたみきを神波は不思議そうに見る。
「ん?」
「.......そんなことがなければ、こうして神波さんと会うこともなかったし.........」
「あ、ああ、そうだね」
「初めて.......が、神波さんみたいな人で、私凄く良かったと思ってますし......」
「え」
みきの小さな声を神波が聞き返したところで、ふいに強い風が二人を襲った。みきはスカートと荷物を慌てて押さえる。飛ばされた昼食のゴミを神波が追いかけてそれを捨てて帰ってくると、先程の言葉をまた聞こうとしてみきの隣に座ったところで彼女の髪に葉っぱがついているのに気付いて手を伸ばす。
「神波さん?」
「髪に......葉っぱが.......」
絡まったくせっ毛の髪。至近距離で視線が合って神波はドキリとして急いで葉っぱをとると彼女から離れる。少しの間二人はお互い膝を抱えて黙っていた。
「........俺さ」
「........はい」
「ずっとあんな生活してきたし、女の子どころか他人にもあんま縁なくて。今も限られた人しか近くにいないし。だから......君といると、なんか安心する」
「...........」
「昔、普通に生きてた頃って思い出したくないけど、やっぱり気にはなるから。君が唯一、今ここにいる俺にそれを感じさせてくれるから」
「神波さん」
「悪い意味じゃないんだよ、それで良かったの、凄く」
「.......はい」
そう言って、ドキドキする気持ちを振払うように神波は勢い良く立ち上がった。
「ちょっと、隣の街の方まで行ってみよっか。俺行ったことないし」
「はい」
みきが埃を払って立ち、鞄を肩にかける。神波は緊張しながらもゆっくりと手を差し出した。彼女は頬を染めて、おずおずと手を伸ばす。
「.........行こっか」
みきに説明されながら街の中を暫く歩いたところで、外人の女がやっている露店に神波はふと足を止めた。一旦繋いだ手を離してしゃがみ込む。品物を少しの間見て、笑ってみきを見上げた。
「...........どれか、買ってあげるよ」
「ええっ、そんな、いいですっ」
「俺も金ないからさ、こんなのしかあげられないけど。綺麗な手なのに何もしてないじゃない、みきちゃん。それともこういうの好きじゃない人?」
ぶんぶんとみきは首を振る。
「そんな、そんなことないですけど、でも.......」
「記念。みきちゃん自分の事俺に話してくれたし、俺も君に話したし」
「.........」
「いっこ選んで」
みきはゆっくりと隣にしゃがんだ。たくさん並んだ指輪の中のひとつを差す。
「........じゃあ、これ.........」
「うん。あ、あの、これ下さい」
「ハーイ、カノジョにプレゼントですねー。2000円になりまーす」
「か.......」
外人の女が笑ってそう言うのに神波はかあっと赤くなった。ポケットから財布を取り出してさっと金を払う。渡されたそれを神波がみきの掌に乗せるのを見て、女は大袈裟に驚いて手を広げた。
「オー、彼、ちゃんと指にはめてあげないとダメですねー」
「お姉さん余計なこと言わないの」
みきが照れながらも言うと女は顔いっぱいに笑顔を作って返す。
「カノジョ良かったですねー、毎度ありがとうございまーす」
「ありがとう」
立ち上がって女にひらひら手を振ると、神波を見て笑った。
「そろそろ、行きましょうか」
「あ、うん、そだね」
右の薬指にその指輪をはめて、みきは嬉しそうに神波に手を伸ばす。またそっと手を繋いで歩き出しながら、神波はこういうことに慣れていない自分を恥ずかしく思いながらも自然に自分と触れあってくれる彼女が嬉しくてひとりで微笑んだ。
太陽がゆっくりと傾いて夕刻を告げる。店の前の街灯のところでみきは徐に手を離すと神波を振り返った。
「あ、私ちょっとお店に用があるんで、ここでいいです」
「うん」
「今日、凄く楽しかったです。ありがとうございました。指輪なんか貰っちゃって」
「俺も楽しかったよ。指輪、そんなんでよかったの?」
グリーンの小さな石がついたそれを神波は見る。みきは自分の指を見つめて嬉しそうに笑った。
「こういうの小さい頃母親の見て凄い憧れてたんです、時代遅れなのかもしれないけど」
「よかった」
「........母親の、婚約指輪がこんな感じで」
「みきちゃん、俺.......」
「はい?」
神波は言いかけてみきとまともに視線が合い、いや、と笑って言葉を飲み込む。
「なんでもない。じゃあ、またね」
「.......ほんとに、ありがとうございました」
「こっちこそ、ありがと」
「またのお越しをお待ちしてます」
みきが笑いながら手を振る。
「はいはい」
神波も笑って返す。みきが軽くお辞儀して店の中へ入って行くのを見届けてから、神波は込み上げてくる嬉しさに緩む口元を押さえながら自分のアパートへの道を走り出した。