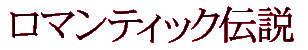
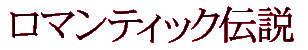
5
あたしは、誰にも欲しがられなかった子供。
15才になった夜、実はあたしは自分達が拾った子なのだとマスターと奥さんに聞いた。
あたしはこのバーの前に、布にくるまれて捨てられていたという。身体は小さかったけど、泣き声だけは元気だったって。マスター夫婦に子供が出来なかったこともあって、彼らはそれは大事にあたしを育ててくれた。物心ついた頃にはここが普通の街とは違う場所だということも分かって、今自分がいるここはこの街を一手に修める大きな組に守られているんだということも知った。時々あるもめ事を片づけにとか、様子を見にやってくる組の世話役やその時まだ若頭だった貴明さんは、見かけこそちょっと怖かったけれどあたしにとっても優しかった。その頃もうそのバーの看板娘的存在になって働いていたあたしにいろいろ教えてくれたし、たまには組員も連れて来て一緒になって騒いだりもしてくれた。時々込み上げてくる自分はひとりぼっちなのだという感情を彼らは忘れさせてくれて、あたしは少しだけ幸せだった。
マスターと奥さんがどこかへ出かけてしまって一晩留守を任されたある日、世話役と貴明さんがやって来た。何か普段と違う空気を感じてあたしが逃げようとすると、貴明さんがあたしの腕をネクタイで縛りつけて、そのまま訳の分からないうちにあたしは世話役に抱かれていた。
もちろん、行為自体の意味を知らなかったわけじゃない。ただ、今までそんなそぶりなど見せなかったその人にそんなことをされて、あたしは恐ろしくて泣きわめいた。それでも世話役はあたしを暴力的に抱いたりはせず、とても優しくしてくれた。終わってから世話役と貴明さんが何事か話したあとで、奥の部屋に連れ込まれて今度は貴明さんに抱かれた。優しくあたしの名前を呼んで、探るように身体を指で辿って、出来る限り負担のないようにあたしを貫いた。
もしかしたら、いつかはこうなることを心のどこかで分かっていたのかもしれない。次第にあたしの声は、ただ泣く声から快感の声に変わっていた。
これはどうやらマスター側とお互い承知の上でのことだったらしい。マスターと奥さんは、帰ってくるなりあたしを抱きしめてごめんねと言い続けた。あたしは笑って二人に言った。
「あたしは大丈夫よ、二人ともとてもあたしを大切にしてくれたから」
それからも時々貴明さんや組の傘下の人間があたしを抱いた。みんな凄く優しくしてくれて、本やドラマで聞いたような優しい言葉をあたしにかけてくれる。行為に慣れたあたしは自分でも恥ずかしいくらい霰もない声をあげるようになって、それが彼らを喜ばせた。マスターや奥さんはたまに辛そうな顔をあたしに見せたけれど、あたしはちっとも辛くなかった。世話役や貴明さんはとても上手だったし、気持ち良さそうな顔をしてくれる彼らやあたしを抱きしめてくれる腕に、こうしてる間だけは少なくともあたしは求められていて、ひとりじゃないのだということを感じていた。
あたしが一浩と会ったのは、それから3ケ月くらいたった頃だ。
世話役がバーに一浩を連れて来た時もやっぱりあたしは奥の部屋で貴明さんに抱かれていて、部屋の前を通り過ぎる彼の目と、ふとあたしの目が合った。強い衝撃にあたしが声をあげたところで彼はふっと目を逸らしてそこから消えた。その、一瞬合った目が、どこかで見たような気がしてあたしは彼が気になった。それが自分の目とそっくりだと気付いたのは大分たってからだ。鏡に映る、求められなかったあたしの目。終わって、シャワーを浴びて出て来た貴明さんにあたしは聞いた。
「さっきの人は誰ですか?」
「ん?......ああ、あいつか。世話役が拾ってきたんだとよ。ここで働かせるらしいぜ」
「.....」
「成井一浩、っつーんだと。ひろ美ちゃんと同い年だぜ。どうしてこうも子供を捨てるやつが多いんかなあ」
「あの人も捨てられた人なんだ.......」
「何の因果かこの街に流れ着いたらしくてね。世話役はあの目が気に入っちまったらしい。確かにガキらしくねえいい目してやがる」
貴明さんはネクタイを締めながらそう言って、ふとあたしを見て笑う。
「......なんだ、気になるんか?」
「だって、歳の同じ人なんてあたし初めて会うし」
「そうか、そうだな。ま、仕事仲間になるんだろうから挨拶でもしとけよ、じゃあな」
くしゃくしゃと頭を撫でてから、貴明さんが去っていく。暫くして勤務の準備のために2階にあがった時、部屋の前であたしはお仕着せに着替えた彼に会った。
「.......こんにちは」
「どーも」
抑揚のない声で彼が返事を返す。初対面であんなところを見られたことにあたしは気付いて何も言わずに黙り込んでいると、彼はあたしを上から下までざっと見て、ぼそっと言った。
「あんた、貴明さんの女なの?」
「......違う、けど......」
「ふうん」
それだけ言って彼は階段を降りて行く。ちょっとだけむかついてあたしはその後ろ姿に叫んだ。
「あんたじゃなくて、ちゃんとひろ美って名前があるんだけど、成井一浩さん」
「.........」
「一応あたし、ここの娘だから。あなたここで働くんでしょ、そんくらいの礼儀通してよ」
彼が立ち止まってあたしを見上げる。
「........宜しく、ひろ美さん」
にこりともせずに彼はそう言って、また階段を降りて行った。
一緒に仕事をするようになってからも、彼の、一浩の態度はあまり変わらなかった。世間話程度に話をするくらいで、面と向かって話した記憶はあまりない。暫くしてマスターや貴明さんに彼の素性を聞いて、その暗い過去が彼をああさせているのだと知った。冷たい瞳。抑揚のない声。それでも、世話役や貴明さんが来た時には、笑顔を見せて楽しそうに話す。意外とかわいらしい笑顔。歳の近い男と触れあうことがなかったあたしは、次第に一浩が気になっていった。何よりひとつ屋根の下に住んでいるというのにあたしを抱こうとしない一浩が気になって仕方がなかった。そんなことを望んでいたわけじゃない。ただ、いつかそうなるのだと思っていたのにそれがなくて、あたしは恥ずかしくも自分に魅力がないのかと悩んでみたりもしたものだ。それとも、誰にでも抱かれるような卑しい女など嫌だったのだろうか。自分を振りかえってくれない彼なのにますますひかれてしまって、ある日意を決してあたしは自分から彼を誘った。抱かれたかったわけじゃない。ただ、一浩の纏う空気が自分と一緒で、誰にも求められてない子供で、そしてあたしが一浩の目に映れば一浩はひとりじゃなくて、あたしもひとりじゃなくなるんじゃないかと思ったからだ。
一浩は、あたしの誘いに笑ってこう言った。
「俺に情けかけてやろうってんなら、それはごめんだからな」
見破られたことにかあっとなって、あたしは思わず切り返す。
「あんただって健全な男でしょ?やりたいと思わないわけ?」
「.........お前、俺とやりたいの?」
冷静に返されてあたしは急に恥ずかしくなって俯いた。一浩はくすりと笑う。
「そりゃあんだけいろんな男にやられてりゃあ身体も欲しがるよな」
「...........」
「慰めてほしいってんならやってもいいぜ。俺だって男だからな、若い女はお前しかいないし、やりたくないわけでもない。ただ、妙な情けかけようってんなら話は別だ」
自分のことばかり考えていてあたしは一浩の歩いて来た道をすっかり忘れていた。この人はずっと情とは縁遠いところを歩いて来たのだ。人に同情されるのを最も嫌っているのだ。自分もそうなのに、どうしてそんな大切な事を忘れていたのだろう。彼の意識に無理矢理自分を組み込もうとしていたなんて。いたたまれなくてあたしはそこから逃げ出したくなったが、頭を切り替えて感情を中に押し込んだ。一浩に笑い返す。
「じゃあ、慰めてよ。あんたの身体も慰めてやるわ」
一浩は口元だけで笑った。
「期待してるぜ」
その言葉にむかついて、強引に彼を押し倒す。その身体を自分の虜にしてやろうと思ったのに、何故かこの男は今までの誰よりも上手くて、感じてしまった自分がちょっと悔しかった。
そんな風に始まったあたしと一浩の関係は、もう16年にもなる。人生の半分をこうして過ごして来たことになる。お互い身体だけ求めていたから、その間何も問題はなかった。簡単にあたしを組み敷くその腕も、セックスも、どこかで覚えて来たようなおざなりな愛の言葉も、全てがあたしを虜にした。情は涌いたけれど、それを出せば一浩が離れていくのを分かっていたからあたしは噫にも出さなかった。ひとりになるのは嫌だった。誰にも、何にも求められなくなることが怖かった。こうして身体を求められるその間だけはあたしはひとりじゃない。誰かの、一浩のためになれる。目の前の全てから、ひとりぼっちの存在から逃げなくてもいい。やがて貴明さんのもとに入った一浩は、感情が研ぎすまされて時々暴力的にあたしを抱いたけれど、あたしはそれでもよかった。一浩のそばにいれるだけでよかった。あたしと同じ、求められなかった一浩。それを指摘することは出来ないし、あたしだってされるのは嫌だから、ただ求められるままにあたしは一浩のそばにいる。身体を捧げて彼を満たして、必要な時にだけそばに寄り添う。ホステス共同で情報を流すのを提案したのもあたしだ。幸い仲間も木梨側をよく思ってなかったからそれは簡単に承諾されたけど、何よりあたしが一浩のためになりたかった。余計な感情を与えようとすれば拒絶される。もしくはきっと殺される。一浩になら殺されても後悔はしないだろうけど、でも、あたしは一浩の枷にはなりたくない。こんなどうでもいいあたしなんかを殺す手間さえかけさせたくない。ただ一浩のそばにいられたら、少しでも一浩の為になれればいい。抱かれるその間だけでも、一浩の意識の中にあたしという存在があれば、それでいい。
「愛してるよ」
気紛れにそんな言葉を囁く彼。あたしの身も心も、簡単に奪ってしまった彼。演じてるみたいなそれに、あたしは笑って返してあげる。
「あたしもよ」
血の匂いのするその身体に、あたしは強く腕をまわした。
薄いシルクのガウンを纏った彼女がコーヒーを入れる姿を、俺はベッドの中から見つめていた。
綺麗にマニキュアの塗られた長い指。その指に光る、ずっと前に俺が気紛れにやったエメラルドの指輪。立て爪の時代遅れのそれを、彼女ははずそうとしなかった。今ならもっと高価なものを買ってやることも出来るし、こいつの稼ぎでもそれなりのやつが買えるのに、当然俺はそんなことはしなかったし、彼女もそうしようとしない。
「はい」
「ああ」
差し出されたカップを起き上がって受け取る。彼女は自分の分を持って、ゆっくりと側の椅子に座った。はだけたガウンから、胸のふくらみが少しだけ覗く。
「木梨の方はどうなの?」
「ああ、思ってたより辛いね。虫酸が走る」
「そう」
「見せてやりたいよ、俺がどんなに苦労してるか」
「それは見物ね、辛そうな一浩なんてそうそう見れないわ」
ふっと笑って俺はコーヒーを飲みながら彼女を見遣る。若い頃から慣らされたその身体は当然ながら、俺はこいつの顔も嫌いじゃなかった。けだるげに見えるがその奥に秘められた強い瞳や、意志の強そうな唇、綺麗なラインの顎、何かたくらんでいるような微笑。その一見強情そうな表情を俺の手で壊してめちゃくちゃに泣かせるのが俺は楽しくて仕方がなかった。
「向こうからは何か入ってくるか」
「ちょこちょこね。そっち大変なんじゃないかって同情してくれるわ。何も知らないでいい気なもんよね」
「じゃあせいぜい大変な振りしときな。あ、煙草くれ」
「はいはい」
口紅のとれかけた唇に煙草をはさんで火をつけて、一度煙を吐き出してから俺に渡す。それを受け取って銜えてから、俺はベッドの縁に座った彼女の腰を抱き寄せて倒した。カーテンから差し込む太陽の光に眩しそうにして、体勢を変えてからカーテンを閉め直す。俺を見てくすりと笑った。
「こんな時間にこんなことしてていいの?」
「......ちょっとくらい遅れたってどうってことねえよ」
「いい身分ねえ、一応新人なのに」
「お前のためにいてやんだよ、ありがたく思いな」
「はいはい、それは嬉しいわ」
半ば諦めたように言葉を返す。俺といることで自然とそうなっているのだろうけど、その物言いも俺は好きだった。俺から離れられないくせに、その大胆な口調。女ながらも貴明さんや組の奴等に堂々と張り合うその度胸。全て俺に繋がっているのだろうけれど、見た目だけではこの女があの以前貴明さんに聞いた過去の持ち主だとは思えない。
時々自分が面白くなる。最も情から離れたところを好む俺が、女と言えばあのおぞましい母親しか記憶のない俺が、どうして彼女を側に置いているのか。彼女が自分に何を求めているのかを承知でこうしているのか。
長い付き合いでお互いの事はもう大抵分かっている。最初に身体を重ねる時点にしたあの契約が、未だに続いているのも凄いことだ。とりあえずは身体の相性もいいし、慣らされたこいつの身体は確かに具合がいい。俺の手に簡単に堕ちる。他に女をつくることくらい出来たが、無駄に人と交流するのは面倒だし、身体だけならこいつ以上の女はいないとも思っている。こいつは契約通り無駄に俺に関わろうとはしないし、俺が望むことは完璧にやってのけた。そんなつもりは全くないのに、こいつが自分の思う通りの女になっていくのを多少楽しんでいるところもあるのかもしれない。
俺もこいつも、誰にも欲しがられなかった子供だ。ただ俺の場合はこいつと違って一応双方合意のもとに生まれたけれど、俺はその事実が最も嫌いだ。あの犯された存在から生まれたことを否定したい。情なんてこの世で最も信じられないものだとも思っている。ひとりの方がよっぽど楽だ。誰の事も気にせずに生きていけるならどんなに楽なことだろう。ただ生きていくにはどうしても時々は誰かを自分の中に交えなくてはいけなくて、それが俺は時々辛くもあった。一瞬でも情を交わすのは辛かった。ある意味「情」によって結ばれた、犯された存在から自分が産まれ堕ちた事実を俺は信じたくない。そうしなければ俺はここにいないのを分かっている。だからこそ、俺は生きることに興味がない。人はひとりになりたくなくて情を交わす。でも、実際人はみんなひとりだ。生きていてもひとりだし、死んでもひとり。どうにも逃げられない。何かから逃げているのを俺は自分で分かっていたが、それを受け入れたくなくて俺はただ生きている。
そして、逃げようとしない彼女が、俺は羨ましいのかもしれない。
俺に全てを捧げようとする彼女。俺なんかに構わなくても、俺よりもっといい男がいるに違いないのに、こいつは俺から離れようとしない。時々その真意を覗かせるが、それを押しやってでも俺の側にいようとする。俺のためになることでこいつは生きている。俺も誰かのためにでもなれたら楽だったろうが、生憎俺にはそんな感情がない。求められるのは面倒だが、まあこいつとは最低限身体だけの関係で保たれている。今さら突き放すのさえ面倒だから、あえて俺はそうしなかった。......そうすることで、真摯に注がれるこいつの感情から、逃げていた。
誰にも欲しがられなかった彼女。
そして俺も所詮求められなかった子供。それを俺はなんとなく分かっていたけれど、俺は無意識にそう思うことを避けていた。それを認めてしまうと、俺の今までの人生全てが否定されそうだからだ。他人と無理に心を交わすよりひとりで生きた方がよっぽど楽だし、いつか死ぬ時に、自分以外の誰かの存在という枷を作るのが俺は嫌だった。そして、他人にも俺なんかの存在を残してしまうのが嫌だった。
それでも。
こんな、今まで何人人を殺して来たか分からないような俺でも、たまには楽になりたかった。殺伐とした場所から離れて、何も考えずにいたい時もあった。そういう時、彼女は格好の場所だった。身体を求めあうだけならば言葉も感情もいらない。何もかも忘れられる。享楽だけに耽っていればいい。彼女といることは俺が最も嫌うはずの、でも結局はどこかで求めてしまっている俺が知るたったひとつの避難の方法だった。柔らかく甘い、俺を求めるその身体と声。こんな俺でも出来ること。彼女の存在を否定しないこと。
俺が唯一、自分の意識の中に存在を認めてしまっている人間。知らないうちに、俺の中に恐ろしい感情を植え付けてしまう人間。
実はいちばん俺が恐れているかもしれない存在。
それが、こんな俺しか見えていないこの可哀想な女だ。
彼女の手が俺に触れる。笑って、指を搦めてやる。気紛れな優しさと身体と言葉に俺は応え、そして彼女が応えてくれる。
その間だけは、彼女は、俺はひとりを忘れられる。